
激安の掘り出し物件が見つかる可能性もあり、
最近市況を賑わしていますよね!
ただし、安い物件は当然理由があります。
ココではワケあり物件の傾向10パターンをおさえて
投資を有利にすすめるポイントをおさえていきましょう!
【無料相談開催中!】中立的な専門家があなたにぴったりな不動産投資や会社をアドバイス
パターン①既存不適格
新築時は合法だったが、建築基準法が変わり用途地域が変更され、制限が厳しくなった地域にある物件で、再建築できないものがあります。
例えば建蔽率や容積率がオーバーしている物件がこれにあたります。
再建築はできませんが、基本的にはリフォームして使い続けることが前提になる物件ですね。
銀行の担保評価も問題ないです。
もう1つのケースは、前のオーナーが違法に許可なく増築してしまった物件ですね。
この場合だと、「建築違反」になり、銀行からの融資は難しくなります。
既存不適格物件の出口戦略(不動産売却のプラン)は、売却益を狙いにくいという特徴があります。
安く購入して利回りを多くとることで、リスクヘッジするという買い方が基本!
パターン②市街化調整区域
自宅であれば建て替えは基本的に可能ですが、アパートなどの共同住宅は立て替えたりすることはできない物件ですね。
パターン③傾斜地
土地の面積の中で、傾斜がある面積(建物を建築できない)がある物件です。
なので、建物を建築できる面積で投資効率効果を判断しないといけないという課題あり。
基本的には指値が必須で、大雨とか大地震で崩壊するリスクもきっちり確認する必要があります。
要壁を後から補強することは、ものすごく費用もかかりますしね。
この手の物件も地震保険や火災保険でリスクヘッジして安く買うことが基本になります。
パターン ④無接道
土地が道路に接している長さ(接道義務違反:2m未満)だと銀行からの担保融資が極めて低くなる傾向があります。
パターン⑤奥行き長すぎ建築不可
自治体によっては、奥行きや建築物の大きさによって2mではなく、3mの接道義務があることも。
例えば、東京都の場合「東京都安心防止条例」で耐火建築物あるいは、準耐火建築物以外の場合で、土地が200㎡以上の場合は、奥行きに関係なく間口を3m以上とらなければいけないと定められています。
埼玉はもっと厳しく、耐火基準は関係なく200㎡以上というだけで3m接道義務があります。
このあたりは重要事項に書かれていない、不動産業者も知らないケースが多く注意する必要があります。
パターン⑥前面道路が私道
前面道路が以下のような私道のケースがあります。
ただし、この私道に共用持ち分として設定(上記の私道をA~Fの土地面積に応じた共有持ち分として設定)されていない場合があるんですよね…
この場合、無接道敷地として銀行から担保評価がでなくなり、借入ができないんです。
また、私道に自分の持ち分があったとしても、銀行の担保が評価が低くなってしまうんですよね
(約50%程度低くなる傾向あり)
つまり、頭金が50%くらい必要になってきます。
また、別のデメリットとしては私道に持ち分があったとしても、上下水管の工事をする際の掘削許可を私道の権利者全員にとらないいといけないんです。
掘削の許可を得られず揉めたり、掘削の承諾料を支払わなければいけないケースもあります。
やっかいなのは、私道の権利者に不動産業者がいる場合は間違いなく金銭を要求される可能性が高いということ。
私道の隣地に接している皆さんのごみ置き場にゴミを置かせないといった意地悪をされるケースもあり、注意事項は多いです。
【無料相談開催中!】中立的な専門家があなたにぴったりな不動産投資や会社をアドバイス
・建物を再建築する場合、上下水道の掘削許可が得られるか
パターン⑦上下水管が隣地に
これは、地主が土地を分筆せずに何棟か立てていたケースが想定されますね。
後日分割して売却する時その切り方によって上下水道管が隣地を通ってしまう場合があるんですよね。
その土地の周辺が一団の分譲地だった場合、その区画を作ったデベロッパーが上下水道管の長さを短くしてコストダウンするために、隣地を通して引き込んでしまうケースがあるんですよね…
建て替え時、隣地の人にそのまま水道管を使わせてくれとお願いしたら、やぶへびになってしまい、購入する時に入れ替えてくれと要求されるケースがあります。
また、戸建の水道管は通常13mmだが、アパートになると13~20mm、20~24mmと太くなるケースがあります。
そうなると、水道管を入れ変える必要ありです。
水道管を入れ変えるコストを考えて、購入判断をしていく必要があります。
パターン⑧借地
借地は、だいたい所有権の価格の約50~60%の値段になっている事が多いですね。
残りの50~40%が底地(地主の持ち分)です。
物件所有者は借地料を地主に払う必要あり(毎月)
建物を建て替えたり、用途を変えたりする場合は承諾料も必要。
1992年8月1日以前に設定された旧法借地権は、20年毎に更新されるが、その借地に建物がたっている以上、地主は借地権の更新を拒否することができません。
旧法借地権であれば、所有権と同じくらい強い権利があるということです。
地主から承諾をもらえれば、非常に安く仕入れられる可能性があります。
ただし、問題がないわけではないんです。
①問題が無いケース
・借地権付き古家をそのまま購入して使う場合は問題なし
・借地権付き古いアパートをそのまま購入して使う場合も問題なし。
★立て替える場合は建て替え承諾料が必要。(新築建物の数パーセント)
②問題があるケース
・用途が変わってしまう場合、地主の承諾が得られないケースあり
⇒古家を古家として使ったり、アパートをアパートとして使うのは問題ないが、古家を買ってアパートに建て替える場合は用途が変わってしまうので、地主から承諾を得られないケースがあります。
逆を言うと、用途変更について購入前に地主の承諾を得ることができれば、借地権付き住宅は非常に掘り出しものになる可能性があるんで必ずチェックを!
ちなみに、1992年8月2日以後は、定期借地権になります。
大型スーパー等は事業用借地権で借地期間後、建物を取り壊して更地にして返さなければいけない、そういう定期借地権が設定されています。
旧法借地権で地主からアパート建設の承諾(用途変更もOK)がとれれば、利回りが20~30%も夢ではないです。
デメリットは、銀行からの融資が物件価格の半分くらいしか受けられないことです。
つまり銀行からの担保評価が出ないということ。
仮に銀行が高く評価しても実際の地主がもっている底地には担保をつけられない。
せいぜい建物に付けるのが精一杯でその建物の担保評価は「固定資産税評価額」相当になるので、土地建物の半分程度しか融資を受けることができない可能性が大きいです。
借地権に投資する場合は、相当の自己資金が必要になることを念頭におきましょう。
【無料相談開催中!】中立的な専門家があなたにぴったりな不動産投資や会社をアドバイス!
パターン⑨事故物件
事故物件とは、自殺や孤独死などで入居者がkりった死亡した賃貸物件を指します。
物件資料の備考欄に「特殊事情あり」とか「心理的瑕疵」と書かれていますね。
この告知義務をしておかないと、買主から損害賠償請求をされる可能性があるからです。
では具体的な告知期間はどの程度必要なのか?
これは、事故発生から約6年ぐらいが目安と言われています。
6年というのは明確に法律で決まってませんが、この6年未満で過去の判例から損害賠償請求が認められる1つの基準になっています。
パターン⑩建物に傾きあり
建物が古くて傾いていたり、雨漏りがひどい、、
そんな欠陥がある場合には、古家として販売されるのではなく、売り土地(古家付き)として売られるケースがほとんどです。
土地として販売しているので、購入後に売主に建物の瑕疵があることを主張できないんですよね。
なので、建物がそのまま使えるかチェックする必要があります。
築40年以上などとても古い物件の場合は基礎が傾いていたり、外装がボロボロで雨漏りがあるケースも….
ただし多少の傾きは、100~200万くらいかければ、ジャッキアップをして元の水平状態に戻すことは可能です。
また、1~2㎝の傾きのレベルであれば、大工工事で床のレベルをフラットにすることができる。
(⇒約30~40万程度かければ、全く気にならない程度の水平にすることが可能)
雨漏りがあるケースも20~30万かければ、雨漏りはストップできます。
なので逆にこのような物件は安く買うチャンスになるということですね!
ワケあり物件10パターン、いかがでしたか?
共通して言えることは、
デメリットがある分、値引きの交渉材料に使える
ということです。
駅から近くて、広くて、価格が安くて、整形地で、、、なんて土地はないです。
掘り出しモノは、値引きによる投資価格を自ら導き出すという作業が大事なんです。
こういった見方でワケあり物件を探してみるのも面白いと思います!
TUNEもなにげなーく参加してみました!(当然、物件購入の申し込みなんて話は無いのでご心配なさらず)





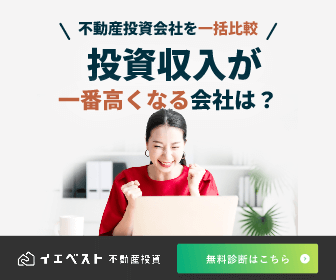


コメント